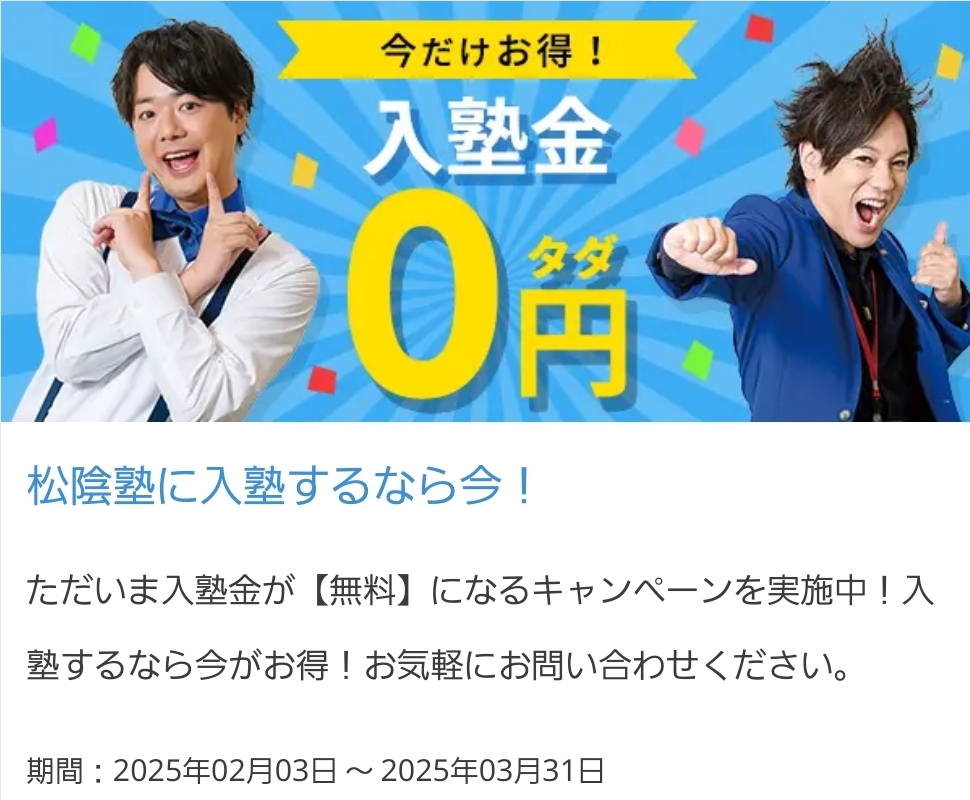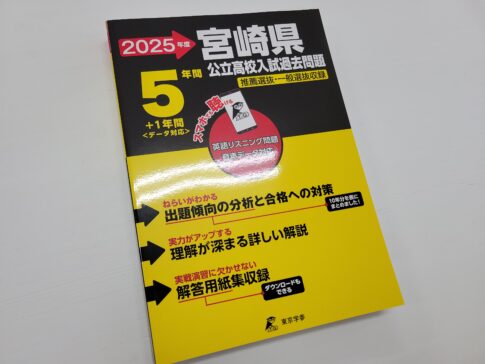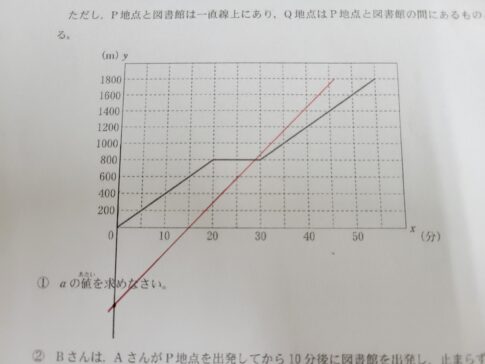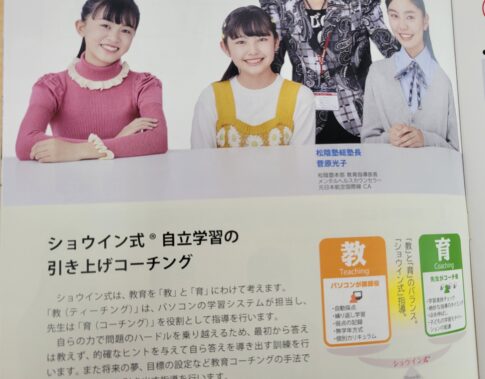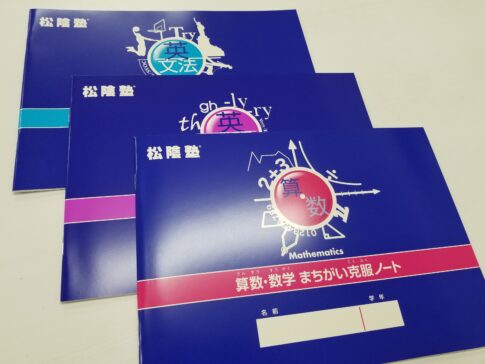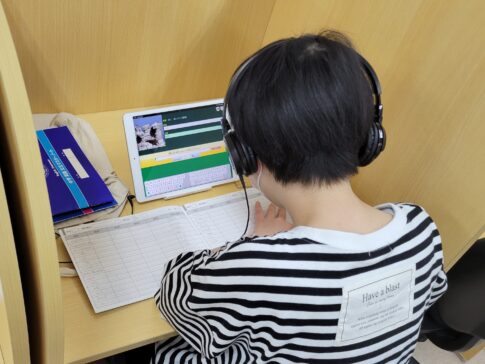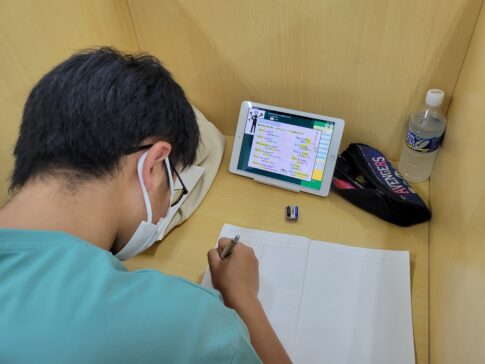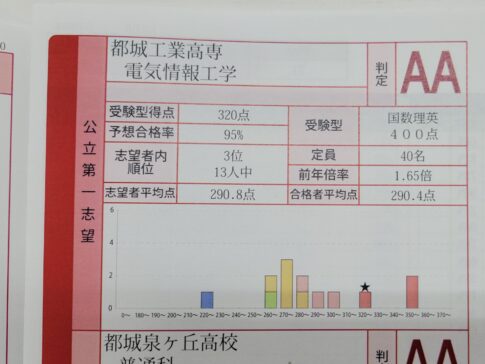県立入試まで残り2週間となりました。
「こんな短期間じゃ何やっても変わらないよ!」
と諦める子もいるでしょうが、そんなことはありません。
この時期でも大きく学力を伸ばす生徒は結構います。
今回はそんな、「学力を伸ばす生徒」たちの共通点について考えてみたいと思います。
「解けない問題」が解けると学力が伸びる
勉強は、普通にやってたらしんどいことも多いです。
カンタンに解ける問題ばかりなら楽しいかも知れませんが、そんなに甘くはありません。
「わからない問題」、「解けない問題」に対してどう向き合うか
で今後の成績が変わってきます。
この場合はどう向き合うのかと言うと、
「解けるようになるまで諦めずに頑張る」
が正解です。
間違えた問題の解説をしっかり読んで、理解する。
そしてまた解く、といった流れです。
「わからない問題」と向き合うのは、それなりの覚悟が入ります。
考えたり調べたりするのに負荷がかかりますからね。
自塾では、「解けない問題のサポート」はもちろんですが、
専用タブレットを使い「一問一答」で問題を解くため、すぐに結果が出るのが特徴です。
すぐに結果が出るのが大事で、
前の問題が不正解だったとしても、解説をキチンと読めば次の問題を正解にすることができます。
なるべくすぐに結果が出たほうが、やる気が出ますからね。
「解けない」と思っていた問題が「頑張ったら解ける」ようになった。
これは自分の限界を超えて成長していると言えます。
「わからない」→「やる気が出ない」→「成績が下がる」→「わからない」…
といった負のループは、最近とても多く見られます。これは何としても避けていただきたいと思っています!
自分の限界を超えると学力が上がる
普通科や高専志望の生徒に対しては、常に「限界突破」を意識させています。
この時のコツとしては、
「ギリギリ解けない問題を解かせる」ことです。
塾ではギリギリ解けるか?解けないかな?くらいの問題を出します。
生徒の学力を把握していないと難しいのですが、
解ける問題ばかり出しても意味はないし、学力と大きく差がある問題を出してもやる気をなくすだけなので。
この時も、解けない問題なので生徒には負荷がかかりますが、
それでも頑張って解けるよう応援するのが塾の仕事です。
これを続けると、自信がついてくるので、自然と限界突破するようになってきます。
今年も、推薦で合格した生徒から話を聞きましたが、
数学は特に「楽しくなった」と言ってくれます。とても嬉しいですね(^^)